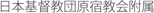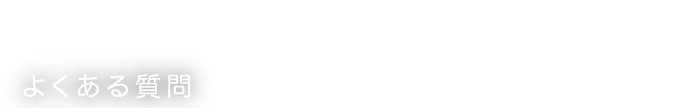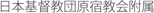

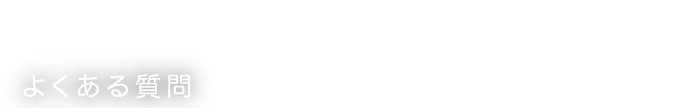
-
クラス編成について教えてください。
-
一人ひとりの子どもを大切にし個性を伸ばすためには、少数制が望ましいとされています。
年齢別のクラス編成ですが、遊びや活動の中では年齢やクラスに関係なく、様々な関わりを持ちながら楽しんでいます。家族や兄弟姉妹のように全員が良く知り合い、互いに交流する中で自己認識や優しさも育ちます。特に各家庭が「少子化」する傾向の中でこのことは大切でしょう。
保育者も自分が担任する子どもだけでなく、全体を把握することを心がけています。
-
保育時間や休日などは、どのようになっていますか。
-
文部科学省「幼稚園教育要領」にある「1日4時間、年間39週」の保育を基準として、次のように実施しています。
-
月・火・木・金曜日
9:00~14:00
-
水曜日
9:00~11:30
-
日曜日(C.S.)
9:00~10:00
-
土曜日
休園日
ただし、行事等の都合で変更することもあります。
「季節休暇」は概ね次のようになっています。
-
①夏休み
7月18日頃~9月1日頃
-
②冬休み
12月18日頃~1月8日頃
-
③春休み
3月17日頃~4月8日頃
*その他、国民の祝祭日等は休園になります。
-
日曜日も保育があるのですね。
-
はい、「礼拝」を中心にした保育を行っています。もちろん私たちは、基本的人権として憲法で保証されている「信教の自由」を充分尊重しています。子どもたちに「信じること」を強要するものではありません。
しかし、私たちの園の「建学の精神」としてのキリスト教を大切にしたいと思います。
子どもたちは礼拝を通して「神様が私たちを愛してくださっていること」を知り、他の人も同じように愛されていることを知って、仲良くすることを学びます。困っている人や苦しみ悲しんでいる人を助け、慰め励ますことができるように成長していきます。
なお、礼拝には「献金」があります。これは「お賽銭」ではありません。これだけ納めるから、これだけのことをしてくださいと神様と取り引きをするのではなく、神様に愛され守られていることへの「感謝」のしるしとして捧げるものです。クリスマスなどには、国内外の援助を必要としている人たちのために、祈りつつ捧げています。
-
建物や設備はどうなっていますか。
-
1998年に新築された園舎は、従来の教室型ではなく、豊かな色彩と遊びの空間を重視しました。子どもたちも、高い天井の広々とした開放的な空間でのびのびと遊びます。
庭は、土や草・芝生などの部分に分かれ、それぞれ自然の特性を体感できるようになっています。
セキュリティーについては、敷地内に防犯カメラ(24時間録画)が設置されています。また、非常通報装置(110番直結電話)、AED(自動体外式除細動器)も設置しています。
ユニバーサルデザイン(バリアフリー)は、「東京都福祉のまちづくり整備基準」適合施設に認定され、国土交通省の冊子「高齢者・身体障がい者等の利用を配慮した建築設計基準」に、幼稚園事例としても紹介されています。
-
給食や通園バスはありますか。
- どちらもありません。私たちは「子どもの生活」を大切にしたいと考えているからです。
小学校になるとほとんどが「給食」になります。幼児期だけでも、家庭の愛に満ちたお弁当を持たせたいものです。健康状態、食欲、好みなど日毎に変化する子どものことが、お弁当箱を洗う時に見えてきます。
幼稚園への道を、子どもと手をつないで歩く時、その日の子どもの心の動きがよくわかるでしょう。子どもと一緒に四季の移り変わりや道筋のいろいろなもの、事柄、動きなどを観察しておしゃべりしてください。そうした中で、自然に多くのものが磨かれます。また、交通ルールなども身についていきます。
-
制服はないそうですね。
又、自由な保育だと聞いていますが。
- 「制服」はありません。自由な服装は子どもたちが動きやすいものを選ぶことができ、またその子らしさも表れます。服装のT・P・Oや豊かな色彩感覚も養われるでしょう。
「自由保育(自由遊び)」とは、自由放任(勝手にさせること)ではありません。子どもたちが「自由に遊びを選び取る保育」を指しています。
子どもたちは、好きなことを見つけ、自分から遊びを作り出していきます。その中で考えたり工夫したり、また友だちとの関わりも生まれます。異年齢の子どもたちが一緒に遊ぶ時、お互いに刺激し合い、模倣を通して、自分の世界を広げていきます。そんな子どもたちの姿を保育者は見守り、時には声をかけ、手助けをしています。
-
家庭との連携はどのようになっていますか。
- 原宿幼稚園では、ご家庭と幼稚園が心を合わせ、共に子どもたちの成長を考え、支えたいと願っています。園からも連絡を密にしますが、ご家庭からも積極的にお話しください。
現代は教育に関する情報が溢れています。まったく相反するような教育論が主張され、親としても思い悩み、迷い、不安や焦りに襲われることもあるでしょう。そんな時、一人で考えるのではなく、親同士や保育者と話すことで、良い判断に導かれることもあるでしょう。
毎月クラス毎に懇談会を持ち、担任からクラスの様子や行事などについてお伝えしています。また、保育参加など集団の中での子どもたちの様子を見ていただく機会を持ち、個別での面談も行っています。
他にも「おしゃべり会」があり、お母さん同士が子育てについて、またいろいろな事柄について自由に語らう場となっています。
また、「預かり保育」を行ったり、地域の教育専門機関と連携して、子育てのサポートをしています。
-
預かり保育はありますか?
- 基本的に、通常保育を行う日の保育時間後に行っています。
月火木金:16:30まで 水:14:00まで (30分¥250)
※必要な時にその都度申し込んでいただきます。
※水曜日は午前保育のため、お弁当を持って来ていただきます。